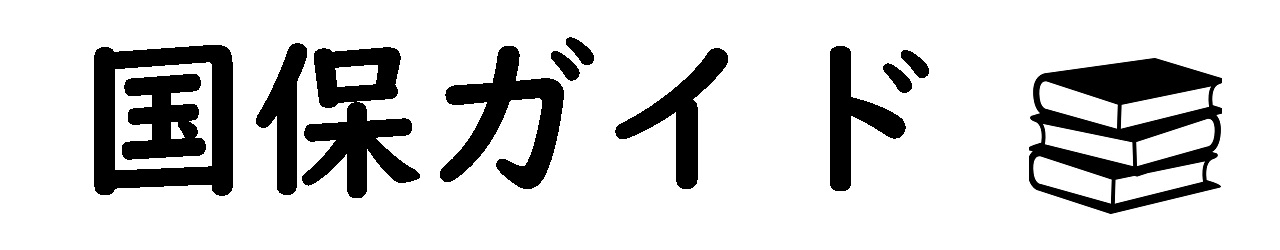国民健康保険や健康保険組合等の医療保険では、70歳以上になると「高齢者」として医療費の自己負担額が変わる場合があります。
では、75歳以上になった場合の自己負担額はどうなるのかご存知でしょうか。
今回は、75歳以上の医療保険や自己負担額についてご説明します。
スポンサーリンク
75歳以上は国民健康保険から後期高齢者医療制度へ。負担額が変わる場合も
日本では、75歳になるとそれまで国民健康保険に加入していた人も、社会保険に加入していた人も全員後期高齢者医療制度に加入することになっています。
この後期高齢者医療制度は後期高齢者広域連合が運営しており、国民健康保険(市町村)とは全く別のものになります(ただし窓口は市町村が担当する)。
ですので、もちろん自己負担額の設定も異なっており、75歳に到達した日から自己負担額が軽減される場合もあります。
75歳以上の自己負担割合
後期高齢者医療制度における、自己負担割合は次の通りです。
現役並み
75歳以上の世帯員に住民税の課税標準額が145万円以上の人がいる場合 ・・・ 3割
一般
75歳以上の世帯員に住民税の課税標準額が145万円以上の人がいない場合 ・・・ 1割
75歳未満の国民健康保険での負担割合は、現役並みが3割、一般が2割となっているため、一般に該当する場合は負担割合が軽減されることになります。
また、収入が現役並みとなる場合でも次に該当する場合は「基準収入額適用申請」を行なうことで、自己負担割合を1割にすることができます。
- 同一世帯の75歳以上の方の収入合計額が520万円未満(単身の場合は383万円未満)の場合
- 75歳以上の方が単身で収入383万円以上でも、同一世帯の70歳~74歳の方との収入合計額が520万円未満の場合
スポンサーリンク
低所得者1・2はさらに医療費の負担が軽減される
後期高齢者医療制度では、同一世帯全員が住民税非課税であった場合、「低所得者1」低所得者2」という区分を設けており、入院時の食事代が安くなる等、医療費がさらに軽減されます。
低所得者の区分に該当するのは次の通りです。
- 低所得者1 ・・・ 同一世帯の方全員が市民税非課税で、その世帯員の各所得が0円(年金収入は控除額80万円で計算)となる被保険者
- 低所得者2 ・・・ 同一世帯の方全員が市民税非課税の被保険者(低所得者1以外)
まとめ
国民健康保険に加入していた人も75歳からは後期高齢者医療制度に移行し、医療費の負担額も変わることが多いです。
医療費の負担割合は移行時に自動的に計算され決定されますが、「現役並み」とされたかたも基準を満たせば1割負担に軽減させることもできます。
知らないと損をしてしまうこともありますので、ぜひ参考にしてください。
スポンサーリンク