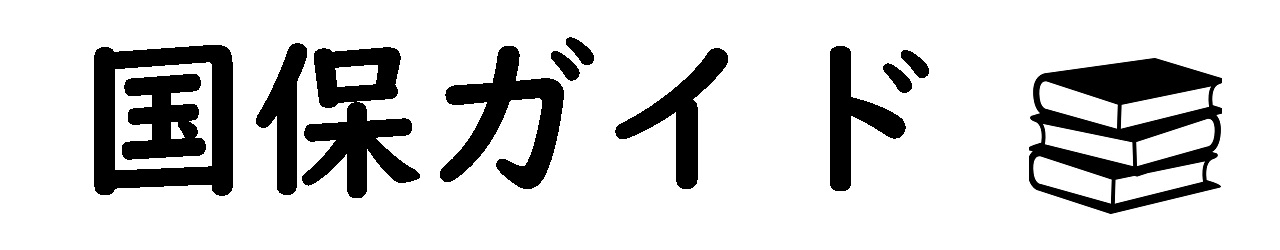長い勤めを終えて、明日からは悠遊自適な生活へ。
と、のんびりしたいところですが、定年退職して会社を辞めたのなら、保険証は会社に返してしまったと思います。
これでは、病院にかかる時にどうすればよいのでしょう。
市区町村のやっている国民健康保険へ加入すれば・・・
ちょっと、待ってください。
まだ、選択肢はありますよ。
スポンサーリンク
退職後の健康保険は、国民健康保険だけではない
退職後の健康保険は、国民健康保険だけでなく、任意継続、誰かの扶養者と選択肢があります。
一般的には、国民健康保険に入る方が多数いるようですが、条件が整っていれば、任意継続や誰かの扶養者になってしまうという方法もあります。
任意継続は、元加入していた健康保険を、事業主が負担していた保険料も負担することにより、2年間継続させる制度です。
保険の効力は、同じでただ保険料が2倍になるというだけです(上限規定あり)。
条件は厳しいですが、誰かの扶養者に入るという方法もあります。
入る先が、社会保険の扶養者の場合、保険料の負担はありません。
金銭的には、一番支出が少なくなるのですが、条件が厳しい(60歳を超えていれば年収で180万円未満等)ため、なかなか加入は難しいです。
特に、退職後に失業保険を貰おうという人は、日額が5000円以下という条件になりますので、ほとんど該当しないのではないでしょうか。
退職後の保険の加入は、どれが一番トクなのか
退職後の保険で一番トクなのは、誰かの扶養者になることです。
しかし、前述のとおり条件が厳しいところです。
となると、国民健康保険か任意継続になるのですが、この2つの保険制度は、大きな違いはないと考えていただいて構いません。
医療機関に受診するとき、医療費が高額になった時などの給付に関する部分に、ほぼ差はありません。
ただ、掛ける保険料の額に差が出ます。
国民健康保険は、前年度の所得金額が算定の元になります。
対して、任意継続は、退職時に掛けていた保険料の2倍(上限規定あり)となります。
こればかりは、個人個人で状況が違いますので、確認の必要がありますが、任意継続の上限規定にかかるような方は、任意継続のほうが、保険料の安い傾向にあります。
ただし、任意継続を選択した場合、2年間は加入し続けることになります。
ということは、前年の所得を元にする国民健康保険のほうが2年目は安くなるというケースもありますので、じっくりと計算する必要があります。
スポンサーリンク
まとめ
定年退職後に加入する保険は、国民健康保険のみでなく、任意継続、誰かの扶養と選択肢があることがお分かりいただけましたでしょうか。
国民健康保険と任意継続の二択になった時は、違いは保険料ですので、じっくりと試算をしてみて、安い保険料の制度へ加入することが大切です。
スポンサーリンク